もう日付が変わってしまったが、昨夜は皆既月食だったらしい。
午後9時45分から一部が欠け始め、同11時6分から11時58分まで皆既月食となった。その後の部分月食は11日午前1時18分に終了。好天の太平洋側などで観測された。
月食は太陽と地球、月が一直線に並び、月が地球の影に入る現象。皆既月食の場合でも、太陽光が地球を取り巻く大気で屈折し、月面にわずかに届くため、赤銅色に見えた。
日本全国で皆既月食が始めから終わりまで起きたのは2000年7月16日以来。次に好条件が整うのは18年1月31日。
らしいのだが、あいにく雲が沢山押し寄せて、撮影できたのは午後10時から午前0時までの間に20分もあっただろうか。

9時頃から準備を始めた。
未だ満月だったが既に雲行きは怪しかった。
機材はペンタックスK200Dに300mmのレンズ。35mm換算で450mm相当。少々心細い。
パナソニックGH-1にFD800mm。35mm換算1600mm。
こちらは、どうなるのか予測がつかない。
露出はF8の30秒位と考えた。
三脚にセットし始めた時はもっと怪しくなっていた。
空模様ばかりか当方も!
手は冷たいし、三脚はその上重い。レンズの台座にネジが上手く入らない、締まらない、暗い。ケーマツルッ。怪しさが充満する。
やっと2基セットし終える頃、部分月食が始まった。
重い、冷たいに耐えながら800mmを月に向ける、何度も向ける。
ファインダーに入って来ない。三脚を一番低くして寝転がって月を探す。ダメだ、腹筋が痙攣している。枕になりそうなものを探す。
あった。しかし月が無い。月は雲の中だ。
苦心惨憺してペンタでようやく撮ったのが、この一枚だ。
甘い誘いも絶ち、「Lunar Eclipse」。彼方からの愁波に酔った。
昨夜は皆既月食だったらしい。
午後9時45分から一部が欠け始め、同11時6分から11時58分まで皆既月食となった。その後の部分月食は11日午前1時18分に終了。好天の太平洋側などで観測された。
月食は太陽と地球、月が一直線に並び、月が地球の影に入る現象。皆既月食の場合でも、太陽光が地球を取り巻く大気で屈折し、月面にわずかに届くため、赤銅色に見えた。
日本全国で皆既月食が始めから終わりまで起きたのは2000年7月16日以来。次に好条件が整うのは18年1月31日。
らしいのだが、あいにく雲が沢山押し寄せて、撮影できたのは午後10時から午前0時までの間に20分もあっただろうか。
9時頃から準備を始めた。
未だ満月だったが既に雲行きは怪しかった。
機材はペンタックスK200Dに300mmのレンズ。35mm換算で450mm相当。少々心細い。
パナソニックGH-1にFD800mm。35mm換算1600mm。
こちらは、どうなるのか予測がつかない。
露出はF8の30秒位と考えた。
三脚にセットし始めた時はもっと怪しくなっていた。
空模様ばかりか当方も!
手は冷たいし、三脚はその上重い。レンズの台座にネジが上手く入らない、締まらない、暗い。ケーマツルッ。怪しさが充満する。
やっと2基セットし終える頃、部分月食が始まった。
重い、冷たいに耐えながら800mmを月に向ける、何度も向ける。
ファインダーに入って来ない。三脚を一番低くして寝転がって月を探す。ダメだ、腹筋が痙攣している。枕になりそうなものを探す。
あった。しかし月が無い。月は雲の中だ。
苦心惨憺してペンタでようやく撮ったのが、この一枚だ。
甘い誘いも絶ち、「Lunar Eclipse」。彼方からの愁波に酔った。
昨夜は皆既月食だったらしい。
<ゆっつら〜と館 T>




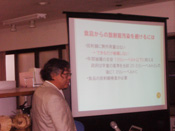
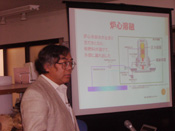
 放射能分解菌は存在しませんが、濃縮除去できる菌はいます。
放射能分解菌は存在しませんが、濃縮除去できる菌はいます。



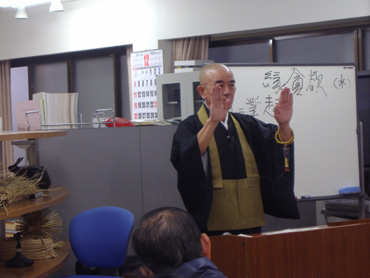

 人は生まれて全ての人は亡くなっていく。人は皆、心(集める)意(考える)識(わきまえる)あり、昔の人は貪欲に底を見ているから強し、地獄、極楽浄土あり、、、
人は生まれて全ての人は亡くなっていく。人は皆、心(集める)意(考える)識(わきまえる)あり、昔の人は貪欲に底を見ているから強し、地獄、極楽浄土あり、、、
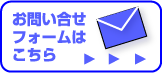
最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)
佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)