
ストック&インスピレーション
鉄製のフックとギアが階段てすりのエンドパーツとして使われている。目にしてしまうと、大した物ではないと思うが。
何処にでもありそうで、滅多に手にする機会のないクレーン等のフックと大型機械のギア。
ストックしていたカリスマのインスピレーションの鮮やかさと豊かさに驚かされる。
客の気を引くフック、かみ合わせを意識してのデザインか。

デザインと町の技術者
これも同店舗の前面を占めている鉄のオブジェである。
相当厚い鉄板が、遠目には革を材料にしたかのごとくに加工されている。この店舗は鉄筋コンクリートの2階建てで周囲の再生された店舗とは趣を異にするが、廃棄物?を活用したことに統一感がある。全景写真を紹介できないのが残念だ。町の技術者が腕をふるったと思われるアイアンワークがいたるところで見られる。
訪れる先々で廃品・廃棄物類を活かした構造物、ディスプレイが目につく。再利用を考えた時、先ず外すことが出来ないモノが鉄であろう。人と鉄には既に約4000年の付合いがある。
アルミ・ステンレス等は防錆性・清潔感に優れ、加工性に富むプラスチックが幅を利かせる時代であるが、人と伴に齢の襞を深めることはない。これらとコンクリートが町の隅々に至るまで多用された時、不老の若さを独り保つ配偶者との間に生じるものの如き、同時代性により添えない切なさ、カラフルを主張する存在の軽さがもたらす虚しさが人を襲うことは無いのだろうか。
「友が皆 我より偉く見ゆる日よ 花を買い来て妻と親しむ」
このような歌がふと過ぎる。
この町を再興したと言われるカリスマ、山野潤一氏に思いを馳せる。
自らの信念への理解を訴える日々があったろう。
カリスマはそれを若者のみに求めたのだろうか。
「鉄は熱いうちに打て」と言われる。鉄を少し扱うようになって、鉄に遊んでもらうようになって初めて知ったことがある。
「鉄は熱くして 打て!」
カリスマは老若問わず、人を熱くし続けたに違いない。
廃棄され錆を帯び、使命半ばにして大地に還らんとする鉄に、もう一度命を形作る鍛冶職人の気質に似た、物に対する深い愛着と炎がそこにあったと想像する。
<ゆっつら〜と館 T>







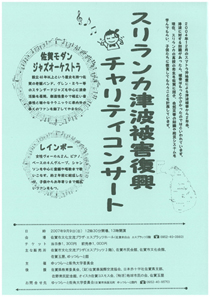




最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)
佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)