
佐賀座はそれこそ、ゆっつら〜と館の“目と鼻の先”にある。
ガラスと銀のうつわ展をやっていたので寄ってみた。

ガラスには独特の軽快さと涼やかさがある。旧い箪笥等の傍に置かれた作品は“ギヤマン”を思い出させる。
ギヤマンは高価で、割れないよう梱包する時に詰められたのが
“詰め草”(クローバー)と言われている。
ガラスの器を見ると
心太(ところてん)を思い出し頭の中が酸っぱくなる。
素麺を思うと空腹感が充満する。
どうも発想と反応が貧困だ。昭和30年代の貧困である。

今日はこのカップでコーヒーをすすった。
松尾重利作「牡丹紋コーヒー碗」だ。
前回も書いたが、どのカップにするか迷うところだが、今回はこのカップが目に飛び込んできた。
作家は今年73歳、若々しい作品だ。

意匠?を同じくする別の作品
コーヒー文化において、上の角ばったスタイルとこの丸みを帯びたスタイルの何れがフォーマル、トラディショナルなのか?
そんな「しきたり」に繋がる拘りが有るのか無いのかも知らないが、
こちらの方がより寛げそうな気がしてならない。
使い分けるか?
しかしながらこれらのカップ、買い求めようと欲すると、廉くはない。
目と鼻の先だ。“囲っている”心算で佐賀座に通うとするか。
<ゆっつら〜と館 T>

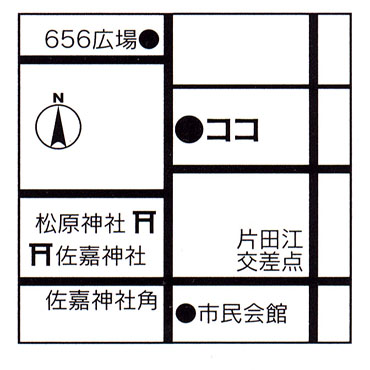




























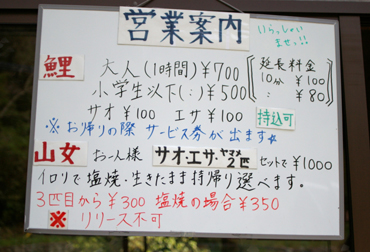





最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)
佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)