9 唐人恵比須
北方、佐賀駅を望み撮影 右手の店舗はTOJIN茶屋
10 寺町恵比須
恵比須さんは、左手の角におられる。奥は城雲院、
初代東京医学校校長となった相良知安の墓がある
11 釣上げ恵比須
12 福恵比須
13 右鯛恵比須
14 文字恵比須
奥の茶色のビルは佐賀銀行、この通りに10〜14の恵比須さんがおられます。
恵比須さんの所在地図を見る
恵比須さん、お顔がモチィーフです
問合せ先
佐賀玉屋 紳士ネクタイ売場
TEL 0952-24-1151(代表)
ふんわりブッセ生地にクリームをサンドしたスイーツです
問合せ先
株式会社村岡屋
TEL : 0120-51-3500
http://www.muraokaya.co.jp
今日はとても風の冷たい日でした
それでも恵比須さんは“にっこり”。
近くの人が供えてくださっているサカキや花などは、外させて貰い撮影しました。
振り返っても、振り返っても微笑む恵比須さん
<ゆっつら〜と館 T>
シリーズ
定時ツアーコース 1 旅立ち恵比須さん
定時ツアーコース 2〜8の恵比須さん
定時ツアーコース 9〜14の恵比須さん
定時ツアーコース 15〜20の恵比須さん
定時ツアーコース 21〜30の恵比須さん
定時ツアーコース 31〜42の恵比須さん



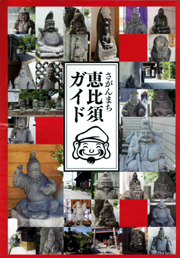
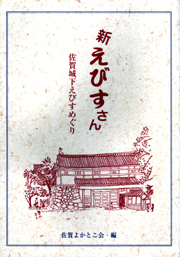






















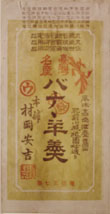
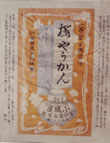
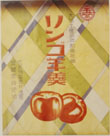


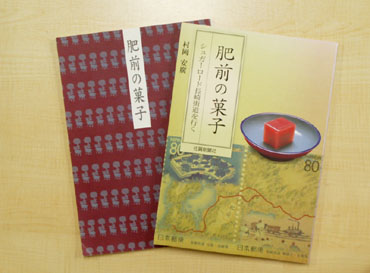




















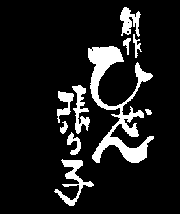


















最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)
佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)