11月3日 掘江(堀ではない)神社の浮立を見に行った。
先輩・後輩がこれに加担?しているのを知ってはいたが、実際間近にするのは初めてである。
神社がある神野(こうの)地区の草場・東神野・西神野の3町区が毎年交代で奉納していたそうだが、近年は東西神野は毎年奉納しているとのこと。草場町区が奉納する年は、3町区が揃うことになる。
地図を見る
神社入り口にある案内板には
佐賀市重要無形民俗文化財 玄蕃一流 昭和43年2月11日指定
この浮立は、弘治2年(1556)5月、大宮司山本玄蕃(げんば)が大干ばつによる雨乞祈願のため、掘江大明神に奉納したことに始まるといわれ、後にこの浮立を“玄蕃一流”というようになったと伝えられている。演者は総勢60有余名からなり、天衝舞、大太鼓、鐘、笛などで構成される。佐賀市郡を中心に今日なお伝承されている天衝舞浮立は、富士町市川の天衝舞浮立や上峰町の米多浮立などがあるが、いずれも山本玄蕃が始めたといわれている。
Furyu Genba Ichiryu (Genba style of dance)
important intangible fork cultural property of Saga City Desighnated Februry 11,1968 Local Saga performing art
in May 1556 YAMAMOTO Genba,the chief priest of Horie jinja(Shinto shrine),created this dance in order to pray for rain.
The dance is performed at the shrine every year on November.
とある。英文での表記にのみ、毎年11月に行われることが明記されているのも面白い。


主役の舞い人が頭上に戴くテンツキ(天衝)・テンツクは、天月、天竺などの文字が充てられる大きな被り物である。
中央の赤い丸は太陽、その左右に龍と月、黄色の丸は星を表わしている。
手にしているのは太鼓の撥(バチ)。腰に着けているのは茣蓙(ゴザ)だが、「大口」と称することもあるようだ。これに関しては諸説ある。後日記述できればと思う。
後方、花笠を被り、締太鼓を叩いているのはモリヤーシ(モリャーシ・モラシ・ムラシ)「盛囃子」を充てる。小学生の5〜6年生。
その後方は鉦打ちの大モリヤーシ。青年男子が当たる。

テンツクの御幣(ごへい)を抜き取り、掌で揉んでから撒き上げる。

横笛6名。なかなか音が出ないらしい。

大太鼓の上に乗せられているのは花嫁布団か


拝殿に向かって左側に女の子のモリヤーシ

右側に男の子のモリヤーシ
男女合わせて20名。大モリヤーシも20名と演者のブログにある。

弁当を手にした少女とすれ違った。もっと近くで撮りたかったが。
町に祭りがある。そしてそこに自分もある。彼女の後ろ姿はそれを教えるかのようだった。
イベントでは得ようがない何かを感じながら、シャッターを押した。
少しピンボケになった。
今回記事アップに際し、背景を知るのに相当時間がかかった。
沢山の人にお世話になった。
佐賀県立図書館の方々。利用法を知らず随分手間をおかけした。
佐賀民俗学会の金子信二さんからは、浮立に関わる沢山の話と資料までも頂戴した。
徴古館では、舞い人の装束に連なる「広口袴」「大口袴」について貴重な資料をいただいた。
皆様に深くお礼を申し上げます。
佐賀市教育委員会発行 佐賀市の文化遺産
佐賀県教育委員会発行 佐賀県の文化財
金子信二著 天衝舞浮立の成立
朝日新聞社文化企画局発行 観世宗家ー幽玄の華
日本経済新聞社発行 三井家伝来の能装束展
株式会社平凡社発行 別冊太陽No.25
西神野浮立・・・・当地の天衝舞演者によるホームページです。
岩崎鬼剣舞□□□北の鬼の復権□□□鬼剣舞いについて
御免町鬼剣舞 隊長日記
衣装・詳細□□□袴□□□袴の種類
先輩・後輩がこれに加担?しているのを知ってはいたが、実際間近にするのは初めてである。
神社がある神野(こうの)地区の草場・東神野・西神野の3町区が毎年交代で奉納していたそうだが、近年は東西神野は毎年奉納しているとのこと。草場町区が奉納する年は、3町区が揃うことになる。
地図を見る
神社入り口にある案内板には
佐賀市重要無形民俗文化財 玄蕃一流 昭和43年2月11日指定
この浮立は、弘治2年(1556)5月、大宮司山本玄蕃(げんば)が大干ばつによる雨乞祈願のため、掘江大明神に奉納したことに始まるといわれ、後にこの浮立を“玄蕃一流”というようになったと伝えられている。演者は総勢60有余名からなり、天衝舞、大太鼓、鐘、笛などで構成される。佐賀市郡を中心に今日なお伝承されている天衝舞浮立は、富士町市川の天衝舞浮立や上峰町の米多浮立などがあるが、いずれも山本玄蕃が始めたといわれている。
Furyu Genba Ichiryu (Genba style of dance)
important intangible fork cultural property of Saga City Desighnated Februry 11,1968 Local Saga performing art
in May 1556 YAMAMOTO Genba,the chief priest of Horie jinja(Shinto shrine),created this dance in order to pray for rain.
The dance is performed at the shrine every year on November.
とある。英文での表記にのみ、毎年11月に行われることが明記されているのも面白い。


主役の舞い人が頭上に戴くテンツキ(天衝)・テンツクは、天月、天竺などの文字が充てられる大きな被り物である。
中央の赤い丸は太陽、その左右に龍と月、黄色の丸は星を表わしている。
手にしているのは太鼓の撥(バチ)。腰に着けているのは茣蓙(ゴザ)だが、「大口」と称することもあるようだ。これに関しては諸説ある。後日記述できればと思う。
後方、花笠を被り、締太鼓を叩いているのはモリヤーシ(モリャーシ・モラシ・ムラシ)「盛囃子」を充てる。小学生の5〜6年生。
その後方は鉦打ちの大モリヤーシ。青年男子が当たる。

テンツクの御幣(ごへい)を抜き取り、掌で揉んでから撒き上げる。

横笛6名。なかなか音が出ないらしい。

大太鼓の上に乗せられているのは花嫁布団か


拝殿に向かって左側に女の子のモリヤーシ

右側に男の子のモリヤーシ
男女合わせて20名。大モリヤーシも20名と演者のブログにある。

弁当を手にした少女とすれ違った。もっと近くで撮りたかったが。
町に祭りがある。そしてそこに自分もある。彼女の後ろ姿はそれを教えるかのようだった。
イベントでは得ようがない何かを感じながら、シャッターを押した。
少しピンボケになった。
今回記事アップに際し、背景を知るのに相当時間がかかった。
沢山の人にお世話になった。
佐賀県立図書館の方々。利用法を知らず随分手間をおかけした。
佐賀民俗学会の金子信二さんからは、浮立に関わる沢山の話と資料までも頂戴した。
徴古館では、舞い人の装束に連なる「広口袴」「大口袴」について貴重な資料をいただいた。
皆様に深くお礼を申し上げます。
<ゆっつら〜と館 T>
今回の記述に際して参考にしたもの
佐賀市教育委員会発行 佐賀市の文化遺産
佐賀県教育委員会発行 佐賀県の文化財
金子信二著 天衝舞浮立の成立
朝日新聞社文化企画局発行 観世宗家ー幽玄の華
日本経済新聞社発行 三井家伝来の能装束展
株式会社平凡社発行 別冊太陽No.25
西神野浮立・・・・当地の天衝舞演者によるホームページです。
岩崎鬼剣舞□□□北の鬼の復権□□□鬼剣舞いについて
御免町鬼剣舞 隊長日記
衣装・詳細□□□袴□□□袴の種類













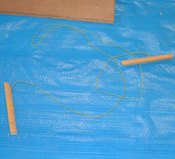










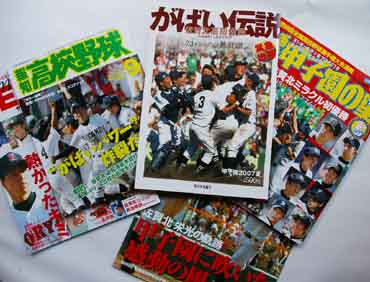

最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)
佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)