先月の半ば頃、四国の吉野川でボタンウキクサが大発生しているとニュースが伝えていた。規模、被害額などをサッとメモしたが、他の件を又サット上書き?して “行き方知れず” に陥っている。
「巧遅は拙速に如かず」と、しばしばやり過ごしては来たが、拙速が致命傷に至るのを自覚は薄いが何度も経験してる。
被害・その他の状況、ボタンウキクサに関する資料を「関連資料」としてリンクするので詳細はそれで確認して頂きたい。
同様の事態が佐賀県佐賀市でも1999年に発生している。
場所は鍋島町八戸(やえ)。
発生地周辺の地図

ポイントA(左の住宅地から狭い農道に架かる橋)から南方を望む。
除去作業が行われる前に撮影したと記憶している。
まだ稲刈りが済んでいない所もある。遠方にビルも見えるが圃場整備もなされていない佐賀ならではのたんぼと掘りである。
あぜ道の幅は60cm位だろう。
ボタンウキクサがびっしりと繁茂している。
アレロパシー作用もあるのだろうか。群落?の様相だ。
ウォーターレタス(Water Lettus)の英名を持つが、厚ぼったく、食感などを言うような代物ではない。
掘りの大きさは、手前、幅20m、約350m先で幅約10m。

ポイントAから 除去作業の様子
船外機付の小船はブイが付いたロープで結ばれており、熊手状のものでかき集めて来る。
重機が使えないので他に方法がないだろう。

ポイントAから
回収チームがロープに絡めて引っ張って来たものをパワーショベルで掬い、トラックに積んでいる。
画面奥は住宅地だが、手前は軽トラックがようやく通れる位の農道に繋がるこれまた狭い橋。

ポイントAから 北方を望む
幅10m、100m先でT字状に分岐している。
ポツンとある濃い緑色はホテイアオイ。

ポイントC(上の画像の奥より左手に伸びた掘りの西端)から ポイントA方面を望む
島状に農地・宅地が入組んでいるので幅は明記しずらい。冒頭の“発生地周辺の地図”で確認して頂ければと思う。
このすぐ後ろは僅か8km足らずで有明海につながる本庄江川。
絨毯を敷き詰めたように繁茂したボタンウキクサ。バシリスクならずとも、ある種の修行を積めば、この上を走れるかも知れない。
冗談はさて置き、と言うか、捨置き、光合成も不可能になり、水中の酸素も欠乏する。腐る過程でも酸素が消費されるだろう。
“水に流す”わけにも行かん!

ポイントB(Aから約140先で右手に伸びる掘りの西端)
幅10m、約140m。手前に見えるのは本庄江川への排水堰。

こんな小さな水路にまで

現在の様子 2008年11月2日撮影
収穫を終えた田んぼが安堵の溜息をついている。
川面の波は深まる秋を知らせる。
佐賀の風景だ。

佐賀市はボタンウキクサの種子の発芽による再発生を考慮し、念入りに除去作業を行ったと思われる。ホテイアオイも見当たらない。
かつてこの掘りには鯉・鮒が沢山いた。産卵時期の早朝には、〜の饗宴を終えてグッタリ?とした姿も見られた。
多布施川から大半を取水していることもあり、上流にある少年刑務所辺りまで鯉の溯上があった。
安部譲司原作であったか、「塀の外で待つ女」主演は大原麗子。
刑務所の前でロケが行われたのは、1988年だったか?
思いの外小柄な、美しい人だった。
冒頭、「巧遅は拙速に如かず」など釈明じみたが、「拙遅」も使い分けている。
実は「移入主種の脅威1」をアップした頃にシリーズとしてボタンウキクサを取り上げる予定が内心あり、佐賀市が除去に際してどれ位の経費を必要としたか問い合わせを行っていた。
返答を下さったTさんには、
遅くなったことを大いに詫びねばならない。
平成11年度に佐賀市が実施した「ボタンウキクサ除去作業」について、下記のとおり回答いたします。
平成11年10月に、鍋島町八戸一帯のクリークでボタンウキクサの大発生が確認されました。
ボタンウキクサは熱帯魚の水槽の水草等に利用されますが、その一部がクリークに廃棄され、異常繁殖したものとみられました。
放置しておくと水路を詰まらせ、水面全体を覆って光をさえぎり、他の水草や生きものの生育・生息を阻害する恐れがありましたので、佐賀市は緊急に除去作業の実施を決定しました。
平成11年10月15日、除去作業を開始しました。主にパワーショベルを使いましたが、道路が狭く重機を入れることができない場所は、職員が船で近づいて集めました。除去したボタンウキクサは、嘉瀬の最終処分場に運んで埋め立てています。
作業は11月までかかり、除去経費は2800万円に上りました。
種ができる時期(冬季)に入る前に徹底的に除去したため、作業終了後、今日にいたるまで、市内ではボタンウキクサの発生は報告されておりません。
現在、佐賀市役所ではホテイアオイの除去作業を継続して実施し、水路の環境保全に努めております。佐賀市の豊かな自然環境を次の世代に引き継いでいくため、市民の皆さまには、今後とも外来種問題に関する理解を深めていただき、適切な取り扱いをお願いしていきたいと考えております。
誠実かつ迅速に返答を頂いた。外来種のもたらす被害に対して市民への訴えもある。
大発生を伝えたのは、ヘラ釣り師 I・Wさんだった。
彼が地元紙に一報したことが、他紙の報道も伴い駆除を実現したと言ってよいかも知れない。生活者が自らの環境に目を向け続けることが、返答にあるように「佐賀市の豊かな自然環境を次の世代に引き継いでいくために・・・。」必要ではないかと思われる。
「芽を摘む」は決して良いことばかりには用いられないが、「目を瞑る」のは好ましくはないだろう。
報道間もなく、鍋島公民館玄関には、水槽に入れられたボタンウキクサと大発生を示す写真を貼ったパネルが展示された。
今夜も長らくお付き合い下さり有難うございます。
大阪市立自然史博物館 淀川河川事務所
旧吉野川河口堰管理所
佐賀県の移入規制種
佐賀県移入種(外来種)駆除活動等補助金
アレロパシー
「巧遅は拙速に如かず」と、しばしばやり過ごしては来たが、拙速が致命傷に至るのを自覚は薄いが何度も経験してる。
被害・その他の状況、ボタンウキクサに関する資料を「関連資料」としてリンクするので詳細はそれで確認して頂きたい。
同様の事態が佐賀県佐賀市でも1999年に発生している。
場所は鍋島町八戸(やえ)。
発生地周辺の地図

ポイントA(左の住宅地から狭い農道に架かる橋)から南方を望む。
除去作業が行われる前に撮影したと記憶している。
まだ稲刈りが済んでいない所もある。遠方にビルも見えるが圃場整備もなされていない佐賀ならではのたんぼと掘りである。
あぜ道の幅は60cm位だろう。
ボタンウキクサがびっしりと繁茂している。
アレロパシー作用もあるのだろうか。群落?の様相だ。
ウォーターレタス(Water Lettus)の英名を持つが、厚ぼったく、食感などを言うような代物ではない。
掘りの大きさは、手前、幅20m、約350m先で幅約10m。

ポイントAから 除去作業の様子
船外機付の小船はブイが付いたロープで結ばれており、熊手状のものでかき集めて来る。
重機が使えないので他に方法がないだろう。

ポイントAから
回収チームがロープに絡めて引っ張って来たものをパワーショベルで掬い、トラックに積んでいる。
画面奥は住宅地だが、手前は軽トラックがようやく通れる位の農道に繋がるこれまた狭い橋。

ポイントAから 北方を望む
幅10m、100m先でT字状に分岐している。
ポツンとある濃い緑色はホテイアオイ。

ポイントC(上の画像の奥より左手に伸びた掘りの西端)から ポイントA方面を望む
島状に農地・宅地が入組んでいるので幅は明記しずらい。冒頭の“発生地周辺の地図”で確認して頂ければと思う。
このすぐ後ろは僅か8km足らずで有明海につながる本庄江川。
絨毯を敷き詰めたように繁茂したボタンウキクサ。バシリスクならずとも、ある種の修行を積めば、この上を走れるかも知れない。
冗談はさて置き、と言うか、捨置き、光合成も不可能になり、水中の酸素も欠乏する。腐る過程でも酸素が消費されるだろう。
“水に流す”わけにも行かん!

ポイントB(Aから約140先で右手に伸びる掘りの西端)
幅10m、約140m。手前に見えるのは本庄江川への排水堰。

こんな小さな水路にまで

現在の様子 2008年11月2日撮影
収穫を終えた田んぼが安堵の溜息をついている。
川面の波は深まる秋を知らせる。
佐賀の風景だ。

佐賀市はボタンウキクサの種子の発芽による再発生を考慮し、念入りに除去作業を行ったと思われる。ホテイアオイも見当たらない。
かつてこの掘りには鯉・鮒が沢山いた。産卵時期の早朝には、〜の饗宴を終えてグッタリ?とした姿も見られた。
多布施川から大半を取水していることもあり、上流にある少年刑務所辺りまで鯉の溯上があった。
安部譲司原作であったか、「塀の外で待つ女」主演は大原麗子。
刑務所の前でロケが行われたのは、1988年だったか?
思いの外小柄な、美しい人だった。
冒頭、「巧遅は拙速に如かず」など釈明じみたが、「拙遅」も使い分けている。
実は「移入主種の脅威1」をアップした頃にシリーズとしてボタンウキクサを取り上げる予定が内心あり、佐賀市が除去に際してどれ位の経費を必要としたか問い合わせを行っていた。
返答を下さったTさんには、
遅くなったことを大いに詫びねばならない。
佐賀市からの回答
平成11年度に佐賀市が実施した「ボタンウキクサ除去作業」について、下記のとおり回答いたします。
平成11年10月に、鍋島町八戸一帯のクリークでボタンウキクサの大発生が確認されました。
ボタンウキクサは熱帯魚の水槽の水草等に利用されますが、その一部がクリークに廃棄され、異常繁殖したものとみられました。
放置しておくと水路を詰まらせ、水面全体を覆って光をさえぎり、他の水草や生きものの生育・生息を阻害する恐れがありましたので、佐賀市は緊急に除去作業の実施を決定しました。
平成11年10月15日、除去作業を開始しました。主にパワーショベルを使いましたが、道路が狭く重機を入れることができない場所は、職員が船で近づいて集めました。除去したボタンウキクサは、嘉瀬の最終処分場に運んで埋め立てています。
作業は11月までかかり、除去経費は2800万円に上りました。
種ができる時期(冬季)に入る前に徹底的に除去したため、作業終了後、今日にいたるまで、市内ではボタンウキクサの発生は報告されておりません。
現在、佐賀市役所ではホテイアオイの除去作業を継続して実施し、水路の環境保全に努めております。佐賀市の豊かな自然環境を次の世代に引き継いでいくため、市民の皆さまには、今後とも外来種問題に関する理解を深めていただき、適切な取り扱いをお願いしていきたいと考えております。
誠実かつ迅速に返答を頂いた。外来種のもたらす被害に対して市民への訴えもある。
大発生を伝えたのは、ヘラ釣り師 I・Wさんだった。
彼が地元紙に一報したことが、他紙の報道も伴い駆除を実現したと言ってよいかも知れない。生活者が自らの環境に目を向け続けることが、返答にあるように「佐賀市の豊かな自然環境を次の世代に引き継いでいくために・・・。」必要ではないかと思われる。
「芽を摘む」は決して良いことばかりには用いられないが、「目を瞑る」のは好ましくはないだろう。
報道間もなく、鍋島公民館玄関には、水槽に入れられたボタンウキクサと大発生を示す写真を貼ったパネルが展示された。
今夜も長らくお付き合い下さり有難うございます。
<ゆっつら〜と館 T>
関連資料
大阪市立自然史博物館 淀川河川事務所
旧吉野川河口堰管理所
佐賀県の移入規制種
佐賀県移入種(外来種)駆除活動等補助金
アレロパシー

































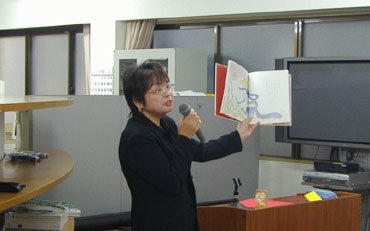













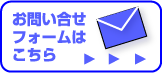
最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)
佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)