| 山野潤一という人物と、共鳴する人達により新たな価値を生み出し続ける上乃裏商店街。 館長以下、ゆっつら〜と館スタッフが視察に訪れたのは先月の25日。時が経つのは早い。 人も町もこの急流に晒されている。 鳴り物入りで開発された箱物さえが、何時の間にか陳腐の謗りを受ける。置き去りにされるのは人だ。 「新しく古くなる」という言葉を聞いた。 古いものを否定するのではなく、古いものの中に、真に必要なものを新たに見出そうという意味と理解している。 前ログでも少し触れたが、いわゆる「新素材」・「新〜」という冠で人を惹きつけ、生活の基盤である町さえも作り変えていく物柄は、タイムプルーフされているとは言い難い。 時の試練を経てはいず、親和性に疑問が残ると言い換えて良いかも知れない。 新しいものを理解せず、受け容れないと言うのではない。 科学と結婚したヒトは元には戻れないのだから。 この町に感じる新旧絶妙の調和は、それを示唆している ように思う。 この町は母のお腹を蹴っている。 怠惰なログに永らくおつきあい下さりありがとうございます。 <ゆっつら〜と館 T> |
 |
 |
 |
 |
2007年10月17日
2007年10月15日
期 間 :10/15〜12/17
毎週月曜日13時〜15時(全10回)
受講料 :1,000円(10回分)
講 師 :鄭仁淑(佐賀大学文化教育学部生)
元気印インさんの人気講座が開講しました!

ボランティア活動に役立てたい・・
韓国旅行を楽しむために受講しています・・などなど
目的はみな様々です。
途中からの受講もできます。
お問合せは、ゆっつら〜と館まで
電話 0952(40)8570
毎週月曜日13時〜15時(全10回)
受講料 :1,000円(10回分)
講 師 :鄭仁淑(佐賀大学文化教育学部生)
元気印インさんの人気講座が開講しました!

ボランティア活動に役立てたい・・
韓国旅行を楽しむために受講しています・・などなど
目的はみな様々です。
途中からの受講もできます。
お問合せは、ゆっつら〜と館まで
電話 0952(40)8570
期 間 :10/15〜12/17
毎週月曜日10時〜12時(全10回)
受講料 :1,000円(10回分)
講 師 :曹宇軒(佐賀大学大学院経済学研究科生)

大人気講座【留学生による中国語講座3】がいよいよ開講しました。
久しぶりの再会に講師の曹君や受講生の皆さんの笑顔が飛び交いました。
初めて参加される方も楽しんでいらっしゃるようでした。
途中からの受講もできます。
ご希望される方はゆっつら〜と館まで問い合わせください。
ゆっつら〜と館
電話 0952(40)8570
毎週月曜日10時〜12時(全10回)
受講料 :1,000円(10回分)
講 師 :曹宇軒(佐賀大学大学院経済学研究科生)

大人気講座【留学生による中国語講座3】がいよいよ開講しました。
久しぶりの再会に講師の曹君や受講生の皆さんの笑顔が飛び交いました。
初めて参加される方も楽しんでいらっしゃるようでした。
途中からの受講もできます。
ご希望される方はゆっつら〜と館まで問い合わせください。
ゆっつら〜と館
電話 0952(40)8570
2007年10月14日
 |  |
| 鯉の死骸に群がるスジエビ。 肉食性である。骨だけになるまで残さず丹念に食べる。そこが 川の掃除屋の一員たる由縁だ。 | 食べたものが透けて見える透明な体。忙しく動き回る、仲間の体の上であろうが何だろうがお構い無しである。 |
ほぼ一ヶ月振りにシリーズを再開する。
この間に松原川の水量は減り、水温も約5度ほど下がり今日あたりは、20度を下回っているかも知れない。
小学1年生の女の子を連れて川辺を歩いてると(当たり前のことだ、常人は水上を歩けはしない)神社北側の太鼓橋付近で、白い物を見つけた。鯉とおぼしき物の死骸だった。
顔を近づけて水中を覗き込むと、2・3cmのエビが群がっていた。スジエビだ。
松原川では、水深があり、なおかつ人がエサをやることにより鯉が集中する参堂正面の太鼓橋辺りを避け、ここ北側の太鼓橋より上流で、石組みがなされた所に多くいるとみていた。
それでも、昨年10月末頃はこれほど簡単には見つけられず、川底に堆積した落ち葉をアテズッポウに網で掬いようやく3匹採れた程度でしかなかった。
近所に住むという40年配のご婦人は「子どもたちが小さかった頃は、エビを捕って一日中遊んでいたのに、エビも魚も少なくなりましたね。」と川と生き物の変貌を残念がっておられた。
それなのに何故これほど沢山のスジエビがいるのか推理した。
昨年と比べ大きな台風も無く、高水温が持続している。
水量も少ない。浅場となったここはもう、鯉の急襲に遭う怖れがない。その上“オカシラ付き”のご馳走がデンとある。
ましてこれは累代の仇の骸である。
「恨み晴らさでおくものか。骨までしゃぶってやる。」と意気込んで馳せ参じた者も多かろう・・・。
連れの小学生と採りにかかる。鯉の肉をたらふく食べて岸辺の石に着いているそやつを、手のひらを揃えそ〜っと引き上げようという算段である。もう顔は水面に着きそうである。
通りすがりの誰かが「あっ、ゴメン」と、尻の辺りに少しでも触れようものなら、落水の憂き目をみるような体勢だ。
そのような失態はなんとしても避けねばならない。
しかし、他人のとは言え子どもの手前採らねばならない。
両手で作った囲みをじわりじわりと狭める。
もう少しで採れる、水面近くまでは持ってこれる。だがそやつは直前に、水と一緒に指の隙間をすり抜け、またあるやつはピンとハネて逃げる。素早くやってみるがなお駄目だ。
石の上だ、膝が痛くなってきた。3年いるか!どうしたものか!
しかし、これ以上の体位も大人としてとれぬ。
それが忘我の境地を拓くとも。
果たして、大人の思慮分別など無用な幼児が最初に捕った。
小さな手で捕った。・・・じっと手を見る。
大人には分別と引き換えに得たささやかな知恵がある。
携帯灰皿をやおら取り出し、洗い、それにエビを入れて幼時に持たせた。怪訝そうなのを大人の器量で無視し、「ゆっつら〜と館の水槽に入れておいで。そして、小さな網があるから持って来なさい。」と半ば言い含めたのだ。
その後は、それこそ掬うように捕れた。道具を使わせたら大人の勝ちである。勝ちに拘るのは大人の性質(たち)である。
そうやって得られたスジエビは、タナゴ・フナ・オイカワ等と一緒に、当館の又してもささやかな水槽で飼われている。
金魚用のエサを与えると、10本の脚を懸命に動かして水面まで上がってくる。
そのしぐさはとてもかわいいが、カラスガイの呼吸口をいじくりまわしたり、魚にまとわりついたりもする。
4本の触覚を持つかなりウザイ奴である。
<ゆっつら〜と館 T>
シリーズ
1.ヤリタナゴ 2.ツチフキ 3.ニゴイ 4.トウヨシノボリ
5.オオスズメバチ 6.ムクドリ+ことりのさえずり 7.ドバト
8.スジエビ 9.ミツバチ 10.コゲラ 11.メジロ
12.松原川の生き物たち号外-1 閉塞・停滞・混濁
13.大きな水槽が欲しい 14.松原川の生き物たち号外-2
15.アオサギ 16.松原川の生き物たち号外-3 撮影について
17.シジュウカラ 18.ツグミ
19.松原川の生き物たち号外-4 撮影機材について
20.カチガラス
2007年10月13日
佐賀大学のSKT君に写真を送ってもらった。
上乃裏商店街の各店がそれぞれ工夫している様子が判る。
携帯で撮ったようだ。送る方は大変だったろうが、使わせ貰う方としては丁度いいサイズで助かった。
最近の記事の内容もさることながら、“諸事重い”傾向と併せて考えれば、この画像容量の軽さは有り難い。
侘びめいたことをせねばならない。
それは9月29・10月9日の記事に関してだが、使っておいでのパソコンの状況によっては記事レイアウトの一部が崩れる。
詳しく言えば、「表示」⇒「文字サイズ」で閲覧する際の文字の大きさが選べるのだが、インターネットエクスプローラー7で初期設定されている「中」以外では綺麗に表示されない。
記事作成中の設定ミスと想われるが是非とも容赦されたい。
パソコンがVISTAならIE7が標準だろうが、ウィンドウズXP以降のものなら、バージョン7以上にアップされる方が良いと想われる。
残念ながら当バージョンは2000には対応していない。
2000のブラウザの最終形はバージョン6のようだ。
当ポータルの読者には“釈迦に説法”であろうが、アイコン「e」にたすきがけのある物はバージョン7と見てよいだろう。
詳細は、ブラウザの「ヘルプ」⇒「バージョン情報」で確認可能。
完全に詫びの様相を呈してきた。
Macでの見え方はどうなっているかも不安である。
このような事こそ先に確認すべきことだったのだが〜。
「長文になることを回避する〜。」という言い訳を用意して今後の対応とさせて頂きたい。
インターネットエクスプローラーのバージョンアップについてはこの辺りを参照されたい。
上乃裏商店街の各店がそれぞれ工夫している様子が判る。
携帯で撮ったようだ。送る方は大変だったろうが、使わせ貰う方としては丁度いいサイズで助かった。
最近の記事の内容もさることながら、“諸事重い”傾向と併せて考えれば、この画像容量の軽さは有り難い。
侘びめいたことをせねばならない。
それは9月29・10月9日の記事に関してだが、使っておいでのパソコンの状況によっては記事レイアウトの一部が崩れる。
詳しく言えば、「表示」⇒「文字サイズ」で閲覧する際の文字の大きさが選べるのだが、インターネットエクスプローラー7で初期設定されている「中」以外では綺麗に表示されない。
記事作成中の設定ミスと想われるが是非とも容赦されたい。
パソコンがVISTAならIE7が標準だろうが、ウィンドウズXP以降のものなら、バージョン7以上にアップされる方が良いと想われる。
残念ながら当バージョンは2000には対応していない。
2000のブラウザの最終形はバージョン6のようだ。
当ポータルの読者には“釈迦に説法”であろうが、アイコン「e」にたすきがけのある物はバージョン7と見てよいだろう。
詳細は、ブラウザの「ヘルプ」⇒「バージョン情報」で確認可能。
完全に詫びの様相を呈してきた。
Macでの見え方はどうなっているかも不安である。
このような事こそ先に確認すべきことだったのだが〜。
「長文になることを回避する〜。」という言い訳を用意して今後の対応とさせて頂きたい。
<ゆっつら〜と館 T>
インターネットエクスプローラーのバージョンアップについてはこの辺りを参照されたい。
Photo
 |  |
| 曲がり角の店 CORNERS 素人が板を打ちつけただけのような外観。イイ雰囲気です | 白い壁と赤い大きな扉の店。 扉を開けるのは、素敵な男のマナーかな? |
 |  |
| 元は事務所だったのだろうか 広すぎる窓面を上手に黒い板で覆っています。 | 上乃裏通りの本通り?のお店。 もともと店舗だったのでしょうか。窓がいい。 |
 |  |
| なまこ壁を想わせるしつらえの店。落ち着いた雰囲気が漂っています。 | 丸く窓を空けた扉と看板のカラーリングが際立つ、ちょっとした感覚がGood。。 |
 |  |
| 今にもエプロン姿の気さくなおじさんが顔を出してくれそうです。 | 国籍不明の存在感がいい。 隠れ家ってとこです。 |
2007年10月12日
第22回 ゆっつら〜と街角大学
テーマ:『ふるさとの川 城原川〜ダムに拠らない治水を探る1』
講 師:元城原川流域委員(田中茶舗・千代田町)佐藤悦子

2003年11月、ダム建設を議論するため県などが設置した「城原川流域委員会」に地元推薦委員として参加された、佐藤さんのお話を聞きました。
次回、10月19日は第2弾を予定しています。
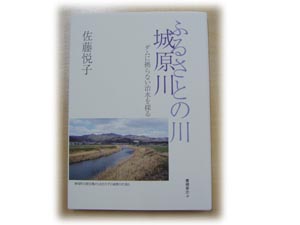
佐藤さんの自費出版された本も購入できます。
ご希望される方はゆっつら〜と館までどうぞ。
(1冊1000円です)
テーマ:『ふるさとの川 城原川〜ダムに拠らない治水を探る1』
講 師:元城原川流域委員(田中茶舗・千代田町)佐藤悦子

2003年11月、ダム建設を議論するため県などが設置した「城原川流域委員会」に地元推薦委員として参加された、佐藤さんのお話を聞きました。
次回、10月19日は第2弾を予定しています。
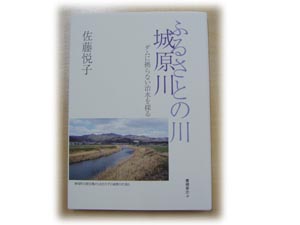
佐藤さんの自費出版された本も購入できます。
ご希望される方はゆっつら〜と館までどうぞ。
(1冊1000円です)
10月11日(木)10時〜12時
期 間 : 7/26〜12/6 毎週木曜日(全20回)
受講料 : 5,000円
(うち3,000円はスリランカ津波被害復興支援に使います)

★10月21日〜10月28日にスリランカより教育者等3名の方々を来佐招待して、自然災害や防災の研修を受けていただくことが決定しました。
〜皆様にご協力頂きました義援金を使わせていただきます〜
期 間 : 7/26〜12/6 毎週木曜日(全20回)
受講料 : 5,000円
(うち3,000円はスリランカ津波被害復興支援に使います)

★10月21日〜10月28日にスリランカより教育者等3名の方々を来佐招待して、自然災害や防災の研修を受けていただくことが決定しました。
〜皆様にご協力頂きました義援金を使わせていただきます〜
2007年10月10日
佐賀大学経済学部 長ゼミナールの様子です<3年生>


〜卒業アルバム用に撮影会〜<4年生>


〜卒業アルバム用に撮影会〜<4年生>
2007年10月09日
第21回 ゆっつら〜と街角大学
テーマ:『「フラット化」時代における地域・空間』
講 師:経済学部准教授 戸田順一郎

昨年、『フラット化する世界』という本が出版されベストセラーとなりました。この「フラット化」とは、情報通信技術の進化により、距離・空間という障壁(カベ)が低くなり、世界が平ら(フラット)になっているということを指します。
では、本当に空間の果たす役割は消滅してしまうのでしょうか?またこのフラット化の進展は、地域にとって何を意味するのでしょうか?そこで、われわれの身近にある一見、空間とは何の関わりもないような経済・社会現象について、「空間」という視点を切り口に捉え直すことを通じて考えてみました。
テーマ:『「フラット化」時代における地域・空間』
講 師:経済学部准教授 戸田順一郎

昨年、『フラット化する世界』という本が出版されベストセラーとなりました。この「フラット化」とは、情報通信技術の進化により、距離・空間という障壁(カベ)が低くなり、世界が平ら(フラット)になっているということを指します。
では、本当に空間の果たす役割は消滅してしまうのでしょうか?またこのフラット化の進展は、地域にとって何を意味するのでしょうか?そこで、われわれの身近にある一見、空間とは何の関わりもないような経済・社会現象について、「空間」という視点を切り口に捉え直すことを通じて考えてみました。

ストック&インスピレーション
鉄製のフックとギアが階段てすりのエンドパーツとして使われている。目にしてしまうと、大した物ではないと思うが。
何処にでもありそうで、滅多に手にする機会のないクレーン等のフックと大型機械のギア。
ストックしていたカリスマのインスピレーションの鮮やかさと豊かさに驚かされる。
客の気を引くフック、かみ合わせを意識してのデザインか。

デザインと町の技術者
これも同店舗の前面を占めている鉄のオブジェである。
相当厚い鉄板が、遠目には革を材料にしたかのごとくに加工されている。この店舗は鉄筋コンクリートの2階建てで周囲の再生された店舗とは趣を異にするが、廃棄物?を活用したことに統一感がある。全景写真を紹介できないのが残念だ。町の技術者が腕をふるったと思われるアイアンワークがいたるところで見られる。
訪れる先々で廃品・廃棄物類を活かした構造物、ディスプレイが目につく。再利用を考えた時、先ず外すことが出来ないモノが鉄であろう。人と鉄には既に約4000年の付合いがある。
アルミ・ステンレス等は防錆性・清潔感に優れ、加工性に富むプラスチックが幅を利かせる時代であるが、人と伴に齢の襞を深めることはない。これらとコンクリートが町の隅々に至るまで多用された時、不老の若さを独り保つ配偶者との間に生じるものの如き、同時代性により添えない切なさ、カラフルを主張する存在の軽さがもたらす虚しさが人を襲うことは無いのだろうか。
「友が皆 我より偉く見ゆる日よ 花を買い来て妻と親しむ」
このような歌がふと過ぎる。
この町を再興したと言われるカリスマ、山野潤一氏に思いを馳せる。
自らの信念への理解を訴える日々があったろう。
カリスマはそれを若者のみに求めたのだろうか。
「鉄は熱いうちに打て」と言われる。鉄を少し扱うようになって、鉄に遊んでもらうようになって初めて知ったことがある。
「鉄は熱くして 打て!」
カリスマは老若問わず、人を熱くし続けたに違いない。
廃棄され錆を帯び、使命半ばにして大地に還らんとする鉄に、もう一度命を形作る鍛冶職人の気質に似た、物に対する深い愛着と炎がそこにあったと想像する。
<ゆっつら〜と館 T>




最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)
佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)