第9回 ゆっつら〜と街角大学
テーマ:私の健康法
講師:郷土史家・元佐賀新聞記者 川浪廣満さん

2月で85歳になられる川浪さんの健康法を参考にして、自分に合った健康法を見つけましょう。為になる楽しいお話をしてくださいました。

テーマ:私の健康法
講師:郷土史家・元佐賀新聞記者 川浪廣満さん

2月で85歳になられる川浪さんの健康法を参考にして、自分に合った健康法を見つけましょう。為になる楽しいお話をしてくださいました。







 菜の花畑
菜の花畑 
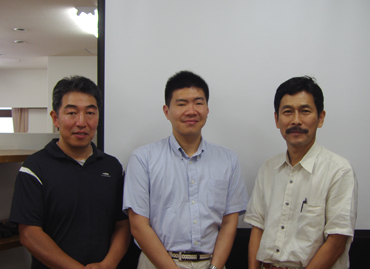

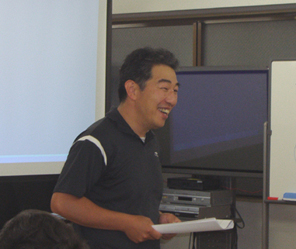





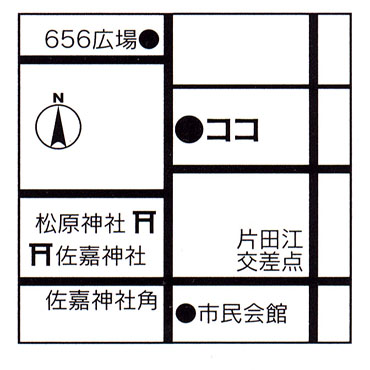 >
>






 店の外観です
店の外観です 店の入り口です
店の入り口です 店内右手です
店内右手です 塩・酢・お茶
塩・酢・お茶 味噌・蜂蜜
味噌・蜂蜜 梅干・加工肉
梅干・加工肉 店内左手です
店内左手です 菜の花畑 蜂は隣の菜の花畑から更に2〜4kmまで遠い菜の花の蜜を求めて飛びます。
菜の花畑 蜂は隣の菜の花畑から更に2〜4kmまで遠い菜の花の蜜を求めて飛びます。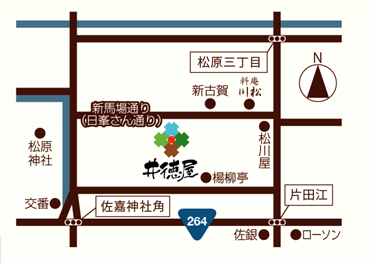




| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)
佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)