 鳩首会談(きゅうしゅかいだん)
鳩首会談(きゅうしゅかいだん)
何時ものパン屋で買ったラスクパンを持って撮影に臨んだ。
思惑どおりに集まってくれるだろうか?
心配は無用だった。パンをまく準備を始めた途端
ワラワラ、クークーと集まってくれた。
タバコの箱ほどの大きさのパンを握りつぶして与えると
写真のような状態であっと言う間に食べてくれる。
鳩首会談とは
このように顔と顔を寄せ合って相談することをいうようだ。
野球のソレは「球種会談」か?
顔ぶれを紹介しよう。写真の上に時計を想定して欲しい。
準備はよろしいか?
12時と6時の位置にいる灰色に二本、黒い線のあるのが
「二引」(にびき)。
7時にいるのは灰色にゴマ状の斑点がある「灰胡麻」。
4時辺りにいるのがゴマの多い「黒胡麻」。
3時にいる翼先端に白い差し毛がある「灰胡麻差し毛」。
11時辺りにいるほとんど黒いのが「シングル」である。
写真にはないが、栗色をベースにした「栗二引」「栗胡麻」
「栗胡麻差し毛」、白をベースに栗色、黒色をまとった「モザイク」などがいる。
「シングル」が“横からクチバシを出して”いる。
何処にでもいるんですねコーユー奴が。
容喙(ようかい)する輩が。
のっけから脱線している。
ドバトはヨーロッパからアジアにかけて棲息していたカワラバトを家禽化(鳥を飼いならすこと)したものといわれている。
愛玩・食料・軍事目的(伝書)が主目的とされ、それらが
「自立」「逃走」「ドロップアウト」「職場放棄」「敵前逃亡」「リストラ」など、事情は彼らにおいても様々だろうが
「快哉」「逡巡」「流浪」の果てに神社などに住み着き、半野生化したものとされ「土鳩」「堂鳩」の漢字が充てられている。
クークー、グルッグル〜?「堂鳩」よもはや悟りを開いたか。
まだ脱線している。
1960年初頭から70年頃まで、多くの少年がハトを飼っていた。二回りほど大きい「食用バト」、純白で長い尾羽がきれいな「クジャクバト」を飼う大人もいた。
ダンボールの箱にハトを入れ、自転車でヒーコラ言って神埼橋まで行き、無事に帰ってくれよと祈りながら放すと、頭上を数回旋回してハトたちは西の方へ飛んで行った。
ヘーコラ言いながら家に帰り着くと、ハトたちはちゃんと帰ってきていた。
優れた帰巣本能により、ハトたちは伝書の役割を担い戦争中多くの殊勲を挙げた。
戦況を左右する機密文書を携えドーバー海峡を渡る伝書鳩
それを待ち構えるのはドイツ軍が放ったハヤブサ〜。
下にリンク張る。
ピースを喫っている方は勿論。嫌煙家も、万難を排して、愛息、愛娘、若い細君を早めに寝かしつけてでもクリックして貰いたい。細君の老若はこの際関係ない。
読み手に用意があれば、涙すら禁じえない生き物の姿がある。
松原神社のハトの数は減ったようだ。郊外に分散したのかも知れない。
10年位前まで、巨勢町玄海橋近くに、純白のハトを沢山飼育している鳩舎(ハト小屋)があった。
式典の際に白いハトを放すのを見られた方も多いに違いない。
ハトは平和のシンボルだった。
知恵を司るミネルバ(ギリシャ神話の女神アテナ)の使いとして知られるフクロウが、やがて疎ましがられたように
ハトもその冠を外されたか。
ハトは今も愛らしい。
機会があれば、そっと彼らを見て欲しい。
より機会があれば、水の飲み方に注意して見て欲しい。
脱線ばかりの長文を、最後までご覧いただき感謝する。
ケータイ使用の方、申し訳ない。
子どもたちは眠りましたか、細君は寝ましたか?
<ゆっつら〜と館 T>
シリーズ
1.ヤリタナゴ 2.ツチフキ 3.ニゴイ 4.トウヨシノボリ
5.オオスズメバチ 6.ムクドリ+ことりのさえずり 7.ドバト
8.スジエビ 9.ミツバチ 10.コゲラ 11.メジロ
12.松原川の生き物たち号外-1 閉塞・停滞・混濁
13.大きな水槽が欲しい 14.松原川の生き物たち号外-2
15.アオサギ 16.松原川の生き物たち号外-3 撮影について
17.シジュウカラ 18.ツグミ
19.松原川の生き物たち号外-4 撮影機材について
20.カチガラス
















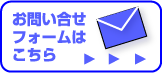
最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)
佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)