「天どこ」で昼食を済ませて、或ることを頼んでいた「展覧会の絵」に向かった。
お店を訪ねるのは初めてだ。
天井が高く、広い店内が印象的だ。
笑みがこぼれる女性に少し遅れて、柔和な面持ちの主人が顔を見せてくれた。
ブログで想像していたとおりだ。
初対面の挨拶を交わし、溶接の話などした。
いろいろな話を聞きたかったが、場違いと想う居心地の悪さが
その間を無くした。
有田へ車を走らせる。「工房陶玲」の釜焚きの祝いだ。
ミシュラン?外部の者による“味の格付け”。その怪しさを思う。
なぜ、自分の五感を頼れないのか?それほど五感は薄いのか
一会で断を下さねばならぬほど、食とそれがもたらす時を削り、
急がなければならないのか。
徒に繰り返される思考を嘲笑するように
ワイパーブレードが軋む。
あの日も同じような小雨交じりの寒い日だった。
「今日は一人ですか?」とケーキ屋の主人は訊いた。
ケーキを日常的に食べる習慣を持たなかった僕は、何時も後ろから押されるようにしてその店を訪ねていた。
同じ時間に授業が終わった時も
銭湯から帰る時も。
何も答えない僕を見て、彼は奥に引っ込んだ。
暫くして
ケーキの入った箱と一通の封筒を手にして現れると
それをしっかり僕にもたせ、その封筒を指し示し
こう言った。
「その中のカードには、ケーキの名前の意味とそれを作った私の気持ちが書いてあります。
それを彼女の前で読んでから、箱を開けて下さい。
二人でこれ迄のように、そのケーキを食べることができたら
あなた達は又うまくやっていける。」
あの日も、小雨交じりの寒い日だった。
お店を訪ねるのは初めてだ。
天井が高く、広い店内が印象的だ。
笑みがこぼれる女性に少し遅れて、柔和な面持ちの主人が顔を見せてくれた。
ブログで想像していたとおりだ。
初対面の挨拶を交わし、溶接の話などした。
いろいろな話を聞きたかったが、場違いと想う居心地の悪さが
その間を無くした。
有田へ車を走らせる。「工房陶玲」の釜焚きの祝いだ。
ミシュラン?外部の者による“味の格付け”。その怪しさを思う。
なぜ、自分の五感を頼れないのか?それほど五感は薄いのか
一会で断を下さねばならぬほど、食とそれがもたらす時を削り、
急がなければならないのか。
徒に繰り返される思考を嘲笑するように
ワイパーブレードが軋む。
あの日も同じような小雨交じりの寒い日だった。
「今日は一人ですか?」とケーキ屋の主人は訊いた。
ケーキを日常的に食べる習慣を持たなかった僕は、何時も後ろから押されるようにしてその店を訪ねていた。
同じ時間に授業が終わった時も
銭湯から帰る時も。
何も答えない僕を見て、彼は奥に引っ込んだ。
暫くして
ケーキの入った箱と一通の封筒を手にして現れると
それをしっかり僕にもたせ、その封筒を指し示し
こう言った。
「その中のカードには、ケーキの名前の意味とそれを作った私の気持ちが書いてあります。
それを彼女の前で読んでから、箱を開けて下さい。
二人でこれ迄のように、そのケーキを食べることができたら
あなた達は又うまくやっていける。」
あの日も、小雨交じりの寒い日だった。
<ゆっつら〜と館 T>










 >「あ〜して、こ〜して。振って、振って。」てんどこ石鹸作り。
>「あ〜して、こ〜して。振って、振って。」てんどこ石鹸作り。





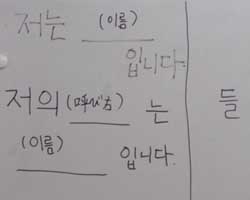



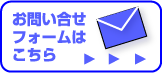
最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
最近の館内の様子(11/6〜11/12) by おい坪田薫警視 (08/17)
佐賀城下ひなまつり巡り6 ひぜん張り子まつばら工房 by ゆっつら〜と館 T (10/07)
佐賀県佐賀市西与賀町で鯉は釣れるの? に応えて by ゆっつら〜と館 T (10/07)